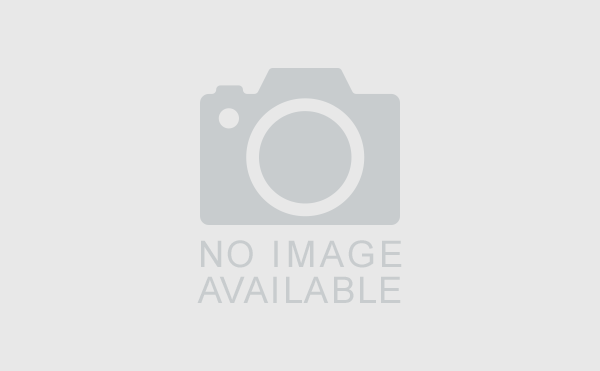10〜20代女性の自殺率増加をどう受け止めるか
〜「比較の価値観」と「生きる理由」を奪う社会〜

10月24日に閣議決定された、令和7年版『自殺対策白書』を読みました。
コロナ禍での自殺率の増加傾向が落ち着きつつある一方で、10〜20代女性の自殺が増えているという、重い現実が示されています。
主な理由は「うつ病や精神疾患の悩み」「学校(学業・進路)に関する悩み」など。
数字の背景にある一人ひとりの苦しみを想像すると、胸が痛みます。
私はこの背景に、SNSの広がりによって生まれた比較と競争の価値観があると感じています。
特に、外見(ルッキズム)と学業・進路の両面で。
10歳前後からスマホを手にし、SNSを通じて常に他人と比べてしまう。
誰かの「美しさ」や「成功」が日常的に目に入る。
さらに、少子化の中で、親自身も競争的な価値観に染まり、子どもに過剰な期待をかけてしまう。
学校でも塾でも、点数と順位で評価される日々。
本来、子どもたちは「あぁ、今日も楽しかった」と感じる日常の中で、
生きることの肯定感を無意識に獲得していく時期のはずです。
思春期には、「自分とは何者か」を考えながら、
自分自身の世界観を少しずつ形づくっていく時間が必要です。
けれど、今の社会ではそこに「比較」が優位に入り込み、
「自分はこうありたい」という姿を描く前に、
「こうあるべき」という外からの基準が刷り込まれてしまう。
その結果、「自分は何者か」「何のために生きるのか」が分かりづらくなります。
ルッキズムと競争主義がより激しい韓国では、
10~14歳の少女の自殺率は、2017年の1.2から2022年には3.2へとほぼ3倍に増加しました。(統計庁・統計研究院(SRI)『Suicide Trends and Responses in Korea』(2023))
日本も韓国を追うように緩やかに増加しています。
日本も同じ道をたどらせてはいけません。
今こそ、大人たちが「何のために生きるのか」を問い直し、
子どもたちに“押しつけない環境”を整えるときです。
具体的なところでは、
・SNSとの付き合い方を学ぶ機会を広げること
・過剰な受験競争を見直すこと
・貧富の差を広げないよう、税金の使い方を変えること
が必要だと思います。
格差が広がるほど、「競争社会で勝ちぬかねば」と、人と比べてしまう。
だからこそ、相談窓口や居場所の開設のように「今困っている人を救う」だけでなく、
社会構造そのものを変える根本的な政策が必要です。
どんな状況になっても、
「笑って生きていける」と思える社会をつくること。
それが、子どもたちの命を守る最も確かな道ではないでしょうか。M